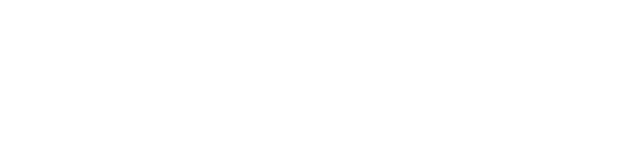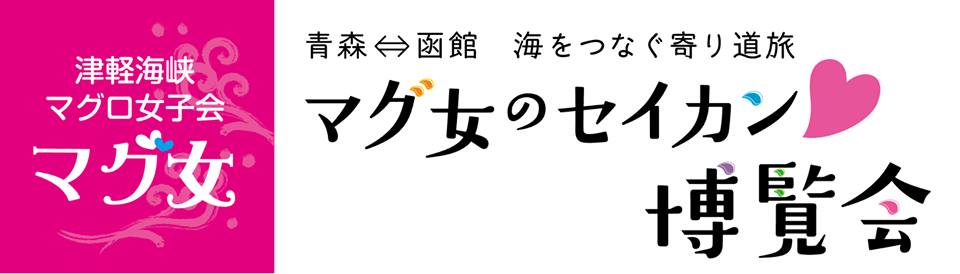大間崎 弁天島クルーズ!始まり始まりーーっ!
2024年度の取組みを活かし、いよいよ本格的なクルーズ事業に突き進みます!慣れた漁師でなければ近づけない「本州最北端の島」だから、漁船に乗ってぐる~と1周クル~ズ!「大間崎 弁天島クルーズ」の始まり始まりーーっ!
主催:大間埼灯台利活用コンソーシアム
共催:日本財団 海と日本プロジェクト
<お問合せ>
事務局:電話0175-37-5073(Yプロジェクト株式会社内 平日9:00~16:00)
-300x127.jpg)
この事業は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で実施しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<2024年度の取組み>
本州最北端の島にある
しろくろ灯台と、シンクロするべ!
キャンペーン
2024年9月14日~10月31日
「本州最北端の地」としてぶいぶい言わしてきた大間崎。その沖合600m先にある島・弁天島で、函館の街並みを背景に白黒くっきりそびえ立っているのが「大間埼灯台」です。泳いで行けそうって思うべさ?クキド瀬戸という激しい潮流や暗礁が点在する海域で、気象条件も悪いから漁船でもなかなか島に上陸できず、灯台が無人化してからはカモメとウミネコの楽園よ。大間崎から軽く眺めるしかなかったこの「しろくろ灯台」のこと、もっと知って仲良くしていぐべしー!


◆灯台とシンクロスナップ◆
しろくろ灯台と写真を撮ろう!
大間崎で白黒なものを身に付けていれば、愉快なシンクロ写真が簡単に撮れます。しろくろ灯台とよりシンクロするためには、ズームを使うのがミソ。
※SNSに投稿する際は、ぜひ「#しろくろ灯台」で。
◆灯台とシンクロフード◆
しましまメニュー
しろくろ灯台サイダーにしろくろマグカレー、弁天島で採った希少な島ひじきや島ふのりにしましま海鮮丼、もぢろんしましまソフトはマストだべ。大間崎でがんばっているお店が、よっしゃ!と考えて出してくれてます。しましまを食べて、灯台とシンクロだー!
◆検証事業:灯台とシンクロフェス◆
2024年9月15日開催!突端フェス!
たぶん、大間崎で初めてのフェスになるでしょう。暑さがやわらいだ秋の良き日、津軽海峡の潮風にあだりながら、みんなで海の向こうの「しろくろ灯台」を愛でる集いです。スペシャルな音楽や食べ物もありあり。人気者のマグロ漁師ペアも、自慢の海歌で盛り上げます。


◆検証事業:灯台とシンクロクルーズ◆
2024年9月14日~16日:しろくろ灯台の島 弁天島クルーズ
ベゴ岩、沖ノマ、ヘフリ崎…。弁天島の外周1.8キロには、わかっているだけで27カ所もの名称が付いています。周囲には岩礁やら入り組んだ潮の流れがあって、慣れ親しんだ漁師でなければ近づけない場所。さあ、漁船さ乗って近づくど!漁師の目になって、海からしろくろ灯台を味わい弁天様にお参りを。

青森県下北郡大間町「大間埼灯台」 江戸時代にも、外国の商船がよく沈没する危険地帯であった大間沖。大正10年(1921年)に初点灯を迎え、海難の歴史がようやく終息しました。以来、不自由な離島暮らしを耐えてきた灯台守のみなさんが、対岸の汐首岬まで17.5キロしかない過密な国際海峡の安全を守ってきた。昼間の海の上でもくっきり目立つよう白黒模様に。「日本の灯台50選」。

弁天神社 大間崎からもはっきり見える、真っ赤なお社。鰐口には正徳5年(1715年)の文字が。灯台ができるまでは、海の安全はひたすら弁天様に祈るしかなかった。津軽海峡が弁天神社の参道だから、今でも漁師たちは、漁船で通過するたびに手を合わせます。灯台と弁天様が対になって、海に生きる人の命を守ってる。